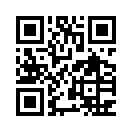2006年07月11日
◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十一)

◆祇園祭(祗園御霊会)とスサノヲの謎(十一)
◆◇◆祇園祭(祇園御霊会)、スサノヲ命(須佐乃男命・素盞嗚尊)と馬頭(駒形)
旧上久世村の氏神である綾戸国中神社(※注1)の御神体の駒形(馬頭)は、スサノヲ命(須佐乃男命・素盞嗚尊)の愛馬「天幸駒」の頭を自ら彫刻して、新羅に渡海の前にスサノヲ命(須佐乃男命・素盞嗚尊)の形見として遣わしたとされている。祇園祭には稚児が駒形(※注2)の御神体を胸に奉持して(久世駒形稚児)乗馬で供奉する。
天神信仰では、農耕の際、雨乞いの祭りをするため、牛や馬を犠牲として捧げたそうだ。そうしたことから、牛・馬は神社と深い因縁がある(「絵馬」は元来、馬の犠牲の名残だ。京都では祈雨止雨の祈祷の際、馬が奉納されたそうである)。古くは、「祇園社」では、牛を祀って天神の怒りを鎮め、疫病を防止しようとした。
(※注1) 上久世という八坂からは遠く離れた地から、祇園祭の重要な稚児が出るのはなぜであろうか。またその氏神である綾戸・国中神社と祇園社の関係はどのようなものであったのであろうか
史料によれば、綾戸社は近世初期には「祇園駒之社」ともよばれ、現在の駒頭はもともと綾戸社と深い関係のあるものであり、また同時にこの駒頭をめぐる信仰が広く流布していたことが窺える。
また、近世の史料に「上久世駒形神人」の名が出てくることから、近世初頭には今日と同様に上久世の人々が祇園祭の神幸祭と還幸祭に奉仕していたことは確かであったようである。
また平安時代末期に書かれたという『年中行事絵巻』の中に、駒頭を胸に抱き、馬に乗った稚児が祇園御霊会の御輿に供奉する姿が描かれていることから、少なくとも平安時代末期には、祇園会に駒形稚児らしき存在が関係していたがわかる。
(※注2) 駒形と言うのは、稚児が首から掛けている馬の首の形をした木製の物である。この駒形を首に掛けて騎乗した時から綾戸国中神社の祭神の化身とみなされた。
八坂神社の神と同格の神の化身であるから、なんびとたりとも許されない騎乗のまま境内に入り、本殿にもそのまま乗りつける事が出来る。(この参代の仕方は長刀鉾の「お稚児さん」にも許されていない)平安時代末の「年中行事絵巻」にも駒形稚児が描かれているように、初期からその存在が確認されている。
スサノヲ(スサノオ)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十九)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十八)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十七)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十六)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十五)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十四)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十八)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十七)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十六)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十五)
◆京葛野の松尾大社と渡来系氏族・秦氏(十四)
Posted by スサノヲ(スサノオ) at 00:00│Comments(0)
│京の民俗学